

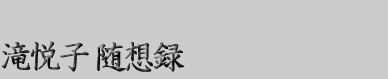



|
筑紫女学園報50号記念 / 寄稿文 「知」の気配に圧倒される歓びを知れ。 この光景を、過ぎ去った三十六年も前の或る午後の一刻を、私の知的体験の第一歩であると確信する。 このたび筑紫女学園報に一卒業生として何かを書く事を依頼されて、私は決して優等生ではなかったし、説教を垂れる柄でもなく、記念すべき50号とはますます荷が重いと怯(ひる)む気持ちが強かったのだが、もしどうしても書き伝えるとしたら「あの『羊の歌』しかない」と瞬時に決めていた。 通常の授業のひとコマを鮮やかな印象として振り返り「為(た)めになりました」と感謝するのが御恩に報いる正しい姿であろうものを、よりによって「規定外授業」が私の後輩に贈るメッセージであるとは。 しかしそれほど強烈な衝撃だった。 教室に響く、先生の伝えようと意図するもののひとつは、おそらく「時代の空気」であったと思われる。 なにしろ当時の、たぶん今も、高校生という一群は、日々自分の周りに展開する家族的矮小出来事に対応するのが精一杯であるからして、いかにも視野が狭い。 そんな泰平の眠りを醒ますような「檄(げき)」でもあった。 「題して『羊の歌』というのは、羊の年(一九一九)に生まれたからであり、またおだやかな性質の羊に通うところもなくもないと思われたからである」と述べる著書の加藤周一は戦後を代表する日本の知識人である。その半生を顧みて回想を綴るという趣向で、六〇年代の一大潮流を形成して熱気のあった『朝日ジャーナル』に連載された。 その、当時好評連載中の最新流行中の週刊誌を、半分は居眠りしてろくろく授業も聞いてない小娘どもに読み与えようとした先生も、思えば果敢であった。 無論、私にしても、即時にその内容を理解したわけではなかった。 漂う知の気配に酔い、また圧倒されていた。 なにやら謎めいた聡明な口調、倫理的な文章の連なり、接したことのない都会の洗練、秘(ひそ)やかな恋の匂(にお)いなどが行間から立ち昇ってきて、胸に沁みた。 「文学には日本現代史そのときどきの最先端が表現されている。文学は時代精神の誠実な証言であり必死の記録であり史料である」 先生はこう言いたかったのだと、今にして思う。 そしてそれは私という一人の生徒にとって、まさにかけがえのない一瞬であり、「読書」を生涯の友とする契機にほかならない。 実はこの際、私の軌跡を検証してやろうと、とっくの昔に紛失してしまった岩波新書版「羊の歌」上下巻を探して回った。 案の定、版元品切れだったけれど六軒目の本屋の片隅で、ひっそりとまるで私を手招きするように懐かしい装丁が並んでいるではないか。 貪(むさぼ)るように読んであらためて気付いたのはその私への影響力の大きさ。 高校生の時分、私は何故か「悪の華」や「ドゥイノの悲歌」を半紙に写して自室の壁に貼り付けていたのだが、これは仏文学を愛好した加藤周一の模倣だったのか。と今頃判明した。また、「ウィーン」を「ヴィーン」と記し、「ワーグナー」を「ヴァーグナーのトゥリスタンとイゾルデ」と記す癖の出所も知れた。 それがどーしたと仰る向きはには声を大にして申したい。 後年になって役に立つのです。特に色恋(いろこい)の場面で女がさり気なく見せる「知識教養」ほど強力な兵器は見当たらない。 現に私は何度も味をしめている。 それを磨くには出発は早ければ早いほど効果的だ。 幸いに私の開眼は高校の授業中だったから、以来私は「活字に潜む歓び」を求めて熱心であり続けている。 「タキさんは、よくいろんなこと知ってますね」とラジオ番組宛に便りを頂くのだが、なぁにその知識のそもそもの大もとはすべて「授業中に学んだ」ことに過ぎないのだ。 例えば、「私は宿命的に放浪者である。私は古里を持たない」と喋って格好イイと誉められたけど、これは国語の時間に習った林芙美子だ。 母親譲りの血ゆえに、共同体に帰属意識を持たなかったと知って、妙に気脈の通じるものを感じた私は早速桜島を訪ねたりした。 五木寛之という「新人」は演歌を艶歌と表すとも教わって瞠目(どうもく)した。 先生は人生の先達である。吸収せねば勿体ない。なにか役に立つこと言わんかなと、耳を澄ませば必ず聴こえる。澄まさなければタダの騒音でしかない。 私は根がケチだから時間を無駄にしたくないのである。 一日に一つでいいから「得した」と感じたいのだ。そのため最短距離は先生からの体得だと考える。 瀬戸内寂聴さんと会ったとき「源氏って典雅で優艶というけど要は危険な恋にしか燃えない面倒な嗜好の」うんぬんと薀蓄(うんちく)を申したら、 「いつからそう思ってたの」 「高校の授業のときに」 「立派ねぇー。そのとおりよ。教えた先生がよかったのね、きっと」
|